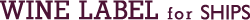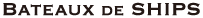2023年秋冬シーズンを皮切りに、
SHIPSのアイデンティティを象徴するスペシャルなニットシリーズが登場する。
そのこだわりのプロダクションとは?
SPECIAL TALK
BATONER Director & Designer
奥山 幸平
SHIPS Product planner
高橋 直樹
Introduction
SHIPSが新たに取り組む究極のニットシリーズプロジェクト。そのパートナーに選んだのは、<BATONER>で言わずと知れた、1951年創業の奥山メリヤス。国内で最も信頼のおけるニットメーカーだ。その3代目であり<BATONER>を始めて10年を迎える奥山幸平氏を招いて、そのプロダクションの背景を探った。
Behind The Scenes
奥山メリヤスと協業するこだわり

高橋 <BATONER>とOEM生産を請け負う奥山メリヤス、現在はどのくらいの割合でものづくりを行っているのですか?
奥山 今は、<BATONER>が約9割になってしまっているというか、なっているというか。奥山メリヤスとしては1割ほどなんです。
高橋 奥山メリヤスさんによるオリジナルのニットって、5, 6年前が最後なんですよね。そのあとのコロナ禍で、いつも通り商品を開発することが気にかかって。ただ消費されるだけの服を作りたくない、かつ、SHIPSのニットはどう在るべきか?――と改めて考えたときに、お客様に何年も着ていただけるアイコニックなニットシリーズを作りたいと思って。そうすると、中途半端なものは作れないし、本物を超えていかなくてはいけない。だから僕は、奥山さんに引き受けてもらえないのであれば成立しない企画だとすら思っていたんです。
Behind The Scenes
時間をかけて実現したプロダクション

奥山 我々が作れる量は限られていますし、流行り廃りのあるなかで、発注側と作る側が今まで通りやるっていう流れは、単に消費されていくだけのものになってしまうというところがあって。そうじゃない、じっくり時間をかけて同じ目線でものづくりをすることが一番重要だし、そういう時代になってきていると思うんです。今回は最初からそこをクリアしていたので。
高橋 通常は半年サイクルでものづくりを行うのですが、2022年の7月に奥山さんとお話をして、時間がかかってもいいからなんとか引き受けてもらえないかという相談から始まり、素材の調達から編み地の企画まで一年かけて作りました。
奥山 このようなサイクルでものづくりを行うのは結構レアケースですよね。でも、限られたキャパシティのなかで、繊細なものづくりができるかどうかが重要で。地球環境のことも含めて、丁寧にものを作って、それを大事に着ていくという価値観を大切にしたいと思うんです。
Behind The Scenes
セオリーから外れることで出る仕上がりの差

高橋 <BATONER>も含めて、奥山さんが作るニットは糸とゲージが物の見事にピタリとハマっているんです。それって実は、めちゃくちゃ難しくて。
奥山 常識から外れていることをかたちにすることにある種こだわりがあって。このゲージだとこの番手で編むでしょっていうようなセオリーがあるんですけど、どこでも作れるものだったらうちでやる必要はない。普通じゃやらないようなことをやるので、シンプルなプロダクトであればあるほど、その仕上がりに差が出るんですよね。
高橋 仕上がりのイメージに近づけていく苦労があると思うんですけど、そのレベルがものすごく高いですよね。
奥山 今となってはある程度自分の知識として蓄積しているものがあるんですけど、日々実験ですね。こうやったら編めるかなとか、こうやったら縫えるかなとか、こういう製品加工をしたらこう上がるかなというようなことを、小回りをきかせて事細かにやっていける環境だからこそできることなんですけど。

高橋 効率を求めると普通はそこまでできない。そこを惜しまずやられているから、表情豊かな商品ができるんですよね。プロダクトとしての完成度が高いから、業界からも一目を置かれていて。イタリアとか海外から来るニット専業の取引先の人たちと一緒にお店にくと、<BATONER>の商品は必ず触るんですよね。訴える強さがあるから。そこには小手先ではない奥山さん流のレシピがあって、それはすごく内包されているものだなと思います。
奥山 自分たちが普段やっていることを、世界中のひとたちがどういう目線で見ているのかはすごく興味があるところですね。
Behind The Scenes
<BATONER>ではなく、
奥山メリヤスでなければならなかった理由

高橋 今回の企画は、<BATONER>への別注ではなく「SHIPS by 奥山メリヤス」でやることにこだわりました。SHIPSのアイデンティティを象徴するニットシリーズなわけですから。その最初に作りたかったのは「チルデンニット」。僕のなかではある意味思い入れが強すぎて、ずっと葛藤していたアイテムなんですよね。
奥山 SHIPSらしいアイテムですよね。逆にいうと、<BATONER>ではあまりやらない商品なんです。そういう意味でも、SHIPSのオリジナルとして展開するという企画自体が意味を持っている、そんな解釈でした。
Behind The Scenes
「チルデンニット」でのこだわり

奥山 まず「チルデンニット」と聞いて、弊社が持っているミドルゲージ・ローゲージのセーターをエレガントに仕上げるみたいなことを掛け合わせたときに、梳毛(そもう)ウールを提案しました。山形は梳毛ウールの産地で、他産地と比べて、ミドルゲージ・ローゲージの風合いを出すのが上手なんです。インフラをアウトプットできるようなことを考えながら、そういうベースもこの「チルデンニット」にうまく落とし込めないかなと思いました。
高橋 膨らみをはっきり出すために限界本数である4本取りにしました。頼りない仕上げにはしたくなかったですし。布帛と違って、1本で編むのか、2本で編むのか、3本で編むのか…自在にできるのがニットの面白いところなんです。
奥山 ただ、値段に結構反映されたり時間にも関わってくることなので、「(コストがかかりますけど)本当にいいんですか?」っていうやりとりを何度もしましたね。
高橋 はい。でも、リミッターを振り切ってしっかりとしたクオリティのものに仕上げるのが今回の最優先事項だったので、他のプロダクションだと考えられないくらい意識しましたし、苦心しました。SHIPSで提供する「チルデンニット」ですから。
Behind The Scenes
ノウハウが詰まった編み地

高橋 「チルデンニット」といえばケーブル編みですが、単調なケーブルにはしたくなかったので、アンカーロープを想像できるような柄や、協業の証として<BATONER>のシグネチャーであるあぜ編みを取り入れました。
奥山 立体的な編み地を表現するのに、針に対して糸の太さを限界まで調整していて、通常だとこのゲージにかからないような番手の糸で無理して編んでいるので、それを撚ろうとしたときに撚れず目がうまく移らないというような現象が起きて、ものにするのにすごく苦戦しました。
高橋 4本取りだと編めないというファクトリーも結構あるんですよね。ただ、奥山さんだったら想像を超えた仕上がりになるだろうという確信があったので、無理を承知で相談させてもらいました。
奥山 頑張りました(笑)。美味しいコーヒーを丁寧にドリップして淹れるように、このニットは自分たちが得意としていることを本当に抽出させている感じです。協業することによって、そういうノウハウをSHIPSのオリジナルにも反映させることができたらいいなと思って作ったのがこの「チルデンニット」です。
エレガントで知的な雰囲気のカーディガン。上品なメタルボタン使いもポイントだ。ネイビーブレザーの代わりに着るような感覚で取り入れたい、洗練されたトラッドスタイルへの最短距離。
- ¥33,000(inc. tax) BUY
カーディガンと同様、複数の編み地で構成されたベスト。配色ライン入りのVネックが爽やかさを印象づける。Tシャツに重ねるだけでも即座にワードローブを更新できる便利なアイテム。
- ¥22,000(inc. tax) BUY